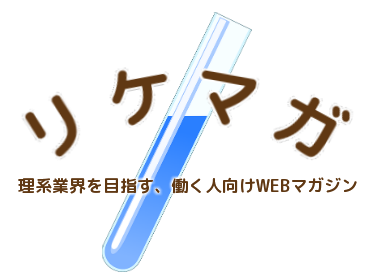実は・・水の挙動に関しての理解は不完全だった
水は私たちが生きていくために、必要不可欠な物であり、水が無くなれば私たちは生きていくことができませんし、その他の動物も植物も命をたもつことが出来なくなります。
水は最も身近で最も人に必要なものとして存在していますが、実はこの生命に必要不可欠な水の挙動については、完全に把握していない状態です。
水と他の液体では温度を下げた場合の密度や熱容量などについて、熱力学的特性変化は違うという事はわかっています。
この水の熱力学的な特性は長く研究されていて仮設についてもいくつか存在します。
その中の一つに、「水に密度が違う二つの相が存在し、その間を揺らぐ」というものです。
しかしよく考えてみると、水は0°を下回った状態では不安定になり凍りつきます。
つまり、この仮説を実証するという検証を行う事が難しい状態だったのです。
そこで理化学研究所放射光科学総合研究センターとストックホルム大学の研究所が国際共同研究グループとして研究を行い、水の構造についての研究をはじめ、「過冷却状態にある水」について構造をとらえるという研究成果を発表しています。
今回の研究は水の研究において画期的な物であり、懸賞が難しかった水について一つの答えを出した結果となりました。
水の構造をとらえる研究とはどういう研究?
今回行われた研究は、X線自由電子レーザー「XFEL」を利用し過冷却様態にした水滴にこのXFELを照射することで構造を調べるという研究だったようです。
このXFELのパルス幅は非常に短く、しっかり冷去れた水が凍りきる前に継続を終えることが出来たため、この研究を行う事が出来たと伝えています。
色々な温度でデータを取り調べてみたところ、水を冷却した時等に起る温圧縮率の症状について、-44℃になると反転する事を突き止めたのです。
水素原子を重水素原子に置き換えた重水「D2O」は-44℃ではなく、-40℃という温度で反転する事もわかり、こうした結果をみる事で、液-液相転移の臨界点「LCP」という部分があるという事を理解できたとされています。
これから先はさらに研究がすすめられ、液-液相転移の臨界点についても明らかにしていくことがポイントになると研究者たちはさらなる水の研究を推進していく意気込みをもっているようです。
水というと、古くから存在しすでに色々な事がわかっていると思っている人が多いと思います。
しかし実際には水という事についてはわからない事も多く、こうした研究を進めている研究者たちが日夜努力されている事も理解しておくべきです。
将来的に水について研究によって判明したことが教科書などに「普通に」掲載されるのかも?など、色々な可能性を考える事が出来ます。